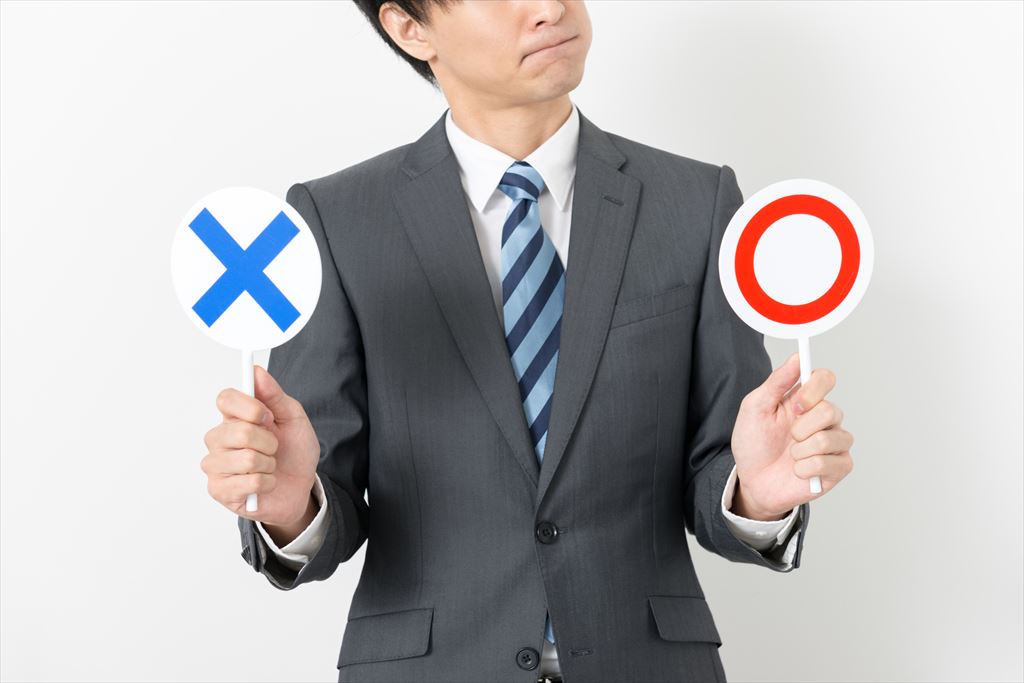※この記事は2020年12月25日に、税制改正にあわせ、内容を一部修正しました。
確定申告の際に、“使っていない経費”が55万円(2019年分以前は65万円)まで認められる制度があります。それが、「家内労働者等の必要経費の特例」です。適用の条件と、適用時の所得の計算方法を解説します。
必要経費の特例に該当する人は?
「家内労働者等の必要経費の特例」に該当するのは、次の人です。
・家内労働法に規定する家内労働者……いわゆる内職をしている人のこと
家内労働者とは、通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいいます。
出典:厚生労働省ウェブサイト
・外交員……保険の営業職員など
所得税法第204条第1項第4号に規定する外交員とは、事業主の委託を受け、継続的に事業主の商品等の購入の勧誘を行い、購入者と事業主との間の売買契約の締結を媒介する役務を自己の計算において事業主に提供し、その報酬が商品等の販売高に応じて定められている者と解される。
出典:国税不服審判所裁決(平11.3.11)
・集金人……NHK、新聞、公共料金の集金を仕事としている人
・電力量計の検針人……電気メーターの検針を仕事としている人
・その他……特定の人に対して継続的に人的役務の提供をする人(国税庁/No.1810 家内労働者等の必要経費の特例より)
特例適用時の所得の計算方法
通常、確定申告では総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて、事業所得または雑所得を計算します。「家内労働者等の必要経費の特例」が適用されると、実際の必要経費が55万円に満たない場合でも、収入金額を上限として、事業所得(雑所得)計算上の必要経費が55万円まで認められます。
<例>
売上=200万円、必要経費=20万円の場合
・通常の所得金額
200万円-20万円=180万円
・特例適用時の所得金額
200万円-55万円=145万円
さらに、事業所得者限定で、青色申告制度と併用することも可能です。その場合は売上から最大120万円もの金額を差し引くことができます。
・特例適用時の所得額/青色申告制度と併用時
200万円-120万円=80万円
実際の必要経費だけを差し引く場合と比較して、課税対象となる所得額は100万円の差があります。所得税率5%、住民税率10%と仮定して単純計算すると、支払う税金は15万円も安くなるのです。
(参考:国税庁 No.1810 家内労働者等の必要経費の特例)
制度活用には手続きが必要
「家内労働者の必要経費の特例」の適用を受けるためには、確定申告書に指定の計算書を添付するなどの手続きが必要です。また、事業所得と雑所得の両方の所得がある場合、ほかに給与所得がある場合は必要経費として計上する額が変わりますので、ご注意ください。
まずは、国税庁のホームページに公開されている計算書を使用して、家内労働者等の必要経費の特例が適用できるかどうかを確認しましょう。適用の場合、確定申告の手続きが複雑になります。あらかじめ計算書を記入の上、税務署でご相談ください。
「家内労働者の必要経費の特例」を適用すると、税額が大きく変化します。条件に該当する可能性がある場合は、迷わず一度、税務署でご確認を!