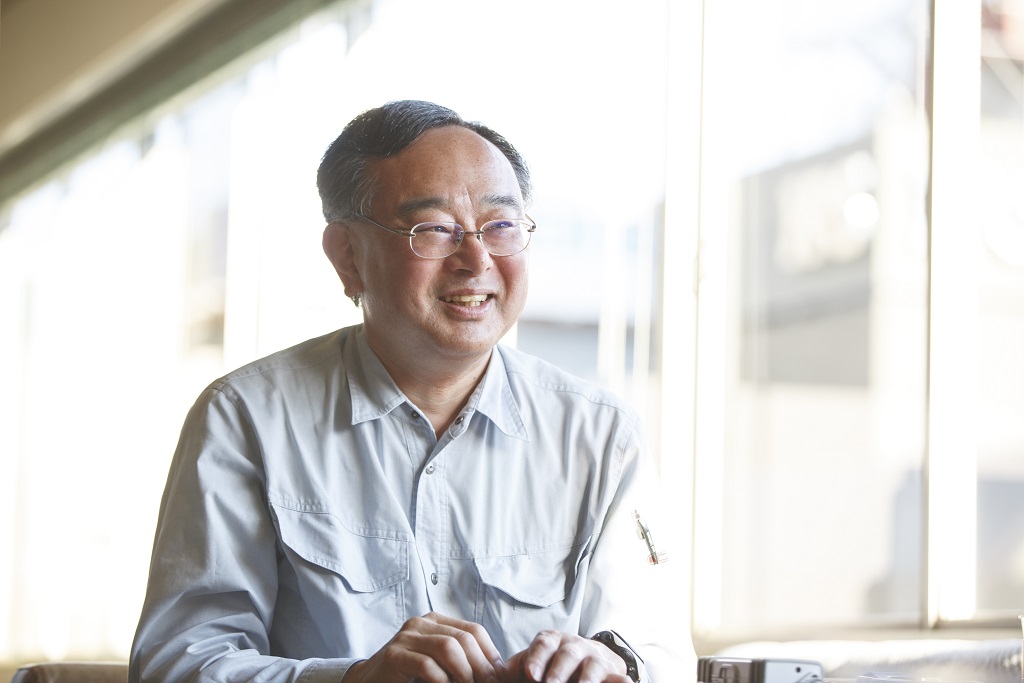建物の躯体構造、外観ではなく、人々が暮らし、働いていく空間を作り上げる内装職人。大工や左官といった建設業の職人たちと同様、スキルやセンス、経験が問われます。
今回お話を伺ったのは、実際の内装工事はもちろん、内装工のマネジメント、ゼネコンやメーカーへのスーパーバイズまで手がける川端俊さん。スキーメーカーから内装業に転身して16年。内装職人の働き方、収支について聞いてみました。
何の気なしに始めた内装業にハマり、修業を経ずに1年で独立
――内装職人といっても業務内容は多岐にわたるといいます。川端さんの担当ジャンルを教えてください。
建物で人の目に触れる内装の仕上げ工事を手がけています。内装には、壁紙やクロス、床のシートやクッションフロア張り、カーペット敷きなど、さまざまな専門領域があります。東京以外の地方では床とクロスを一緒に手掛ける職人もいますが、僕は床の仕上げをメインに手がけています。
知人の紹介で町の飲食店を個人で担当することもありますが、大型集合住宅とか大型商業施を手がけることが多いですね。主業務は大手建築会社、いわゆるスーパーゼネコンと呼ばれる企業が手がける建物の内装の職長。多くの職工を取りまとめ、指揮するのが仕事です。
多くの人にとって、一生で一番大きな買い物である住宅をハイクオリティな仕上げ工事で引渡したい。家族が楽しい時間をわかちあうショッピング空間を手がけたい。それがモチベーションの原点にありますね。

――内装職人になるには、どんなルートが一般的なのでしょうか。
職人の下に付いてキャリアを積み、10年ぐらい下積みを積んでから独立するのが一般的ですね。ただ、僕は修行らしい修行をしてきていないんですよ。
もともとはスキーの選手をしていて、現役を離れてからは所属スキーメーカーに勤務。ところが、レジャー業界は長い不況に突入。スキーメーカーも販売促進活動を縮小していくことになったので、僕は自らの意思で退職しました。
しばらく休んで次の進路を考えようかと思ったら、地元の先輩で内装業をしている人が「人が足りなくてさ、暇ならちょっと現場を手伝ってよ」と言ってきたわけです。ぶらぶらするのも何なので、現場で資材を運んだりするのを手伝っていたら、勧められるままにシート張りにトライすることに。見よう見まねで張ってみたら、1年ぐらいでほかの職人さんぐらいのレベルになっていました。
作業員として現場に入っても、効率の良い段取りを提案していると、いつの間にか建設部門の監督とやりとりをする流れに。内装職人を自然にまとめることが多くなっていったんです。こうして、周囲に推される形で2年目には独立。現在16年目になりますね。

――修行を経ずしてシート張り、職人の取りまとめを手がけるようになるとは。もともと器用だったんでしょうか?
スキーに没頭していた自分としては、シート張りの作業はそれほど細かい作業とは思えなかったんです。スキーは板のワックスがけやビンディングの調整など、チューンナップが生命線。内装業のシート張りも、確かに細密です。ミリ単位で調整しなければ満足いく仕上がりにはなりません。ただ、ミクロの単位で調整してきた身にとっては、飲み込みやすかったのは確かですね。
そして、僕の実家は建築事務所。小学生の頃から夏休みには測量を手伝ったり、図面を引いてみたりしていました。建築現場にはなじみがあったんでしょうね。
あと、選手を引退後は販促を手がけていたので、交渉・折衝はお手の物。現場の監督さんとすりあわせていくのが向いていたんです。そのコミュニケーション、調整って、職人肌の人が最も苦手とするところですからね。「川端さんにまとめてもらって指示を受けたほうがやりやすいよ」と言ってくださる職人さんが次第に増えていったんです。

職人の立場になって考え、日当や振込サイトを調整する
――内装の職長として活躍される川端さんですが、いわゆる一人親方として働いていますよね。ゼネコンなどの大口の仕事はどのように受けられているんですか?
ゼネコンの内装仕事は一次請け、二次請けという流れを経て職工に回ります。一次請けは、ほとんどが壁面のクロス張りを手がける会社ですね。床張りを含めて内装を請けてもクロスしかやらないんです。僕は二次請けとして床張りの内装職人を集め、現場を取りまとめます。
一次で請けると500人の人工(1人の作業員の1日の仕事)がかかるし、材料費も立て替えなければならない。大手の仕事だと経費だけで億単位になるので、ちょっとリスキーな額面になります。だから、一次請けをワンクッション入れるのが僕のようなポジションとしては安心です。大手ゼネコンも建設ばかりではなく改修工事を手がけることもあるんですが、そのときは予算も小回りのきく範囲内。僕が一次でダイレクトに請けることもありますね。
――現場の費用感、予算はどのように決まるのでしょうか。
担当するフロアの平米数×人工が基本的な見積もりです。だから、現場調査しておけば簡単に見積もりが出せます。ただ、改修工事などは予想外の残置物があったり、天候不順や風が強い現場で工期が延びたり、ケースバイケースです。建築のフローとして、基礎工事や外壁の工事が上流ですから、内装は工期も予算も最後に割り振られます。最もしわ寄せがくる業務なので、平米数だけで単純に見積もるのは危険。現場調査、トラブルを織り込んだ見積もりには神経を使います。

――ケースバイケースだとは思いますが、内装職人の日当はどれぐらいが相場になりますか?
二次請けによってさまざまだとは思いますが、うちは日当2万3,000円を出しています。親方クラスだと2万5,000円、若手には2万円だったりしますが、ならすと2万3,000円。数年前はもう少し高く設定できていましたが、現在はこのあたりが一般的でしょうね。
もちろん、うちが一次請けのときは案件の総額も増えてより多くを回せますが、その一方で予算から日当2万3,000円を出せない現場も少なくありません。そこで、現場によって不公平感が出ないように、一次請けでは予算をプールし、低い現場で補填しています。

予算をプールしているのは、まっとうに振り込めるためでもあります。一次請けの多くの支払サイトは40日。月末締めの翌々月10日払いが一般的です。だけど、うちが頼んだ職人には月末締めの翌月末振込に設定しています。家計を預かるご家族にしたら、月末に入金があるのと翌月10日に振込があるのとは全然違うでしょう。当初は25日振込にしていたのですが、それではさすがに僕の方もキツかったので、月末に設定しています。
大事にしているのは、振込も銀行に足を運び、自分でやること。手間を考えたらモバイルバンキングでささっと済ませるほうがいいんでしょうが、ATMの前に立っていると「あいつの現場は遠かったから、サービスエリアのご飯代ぐらい乗せてあげようか」とかね、いろんな思いが湧いてくるんですよ。正当な対価、経費を支払いつつ、ほんのちょっとの気持ちを乗せる。僕が現場で助けられ、困ったときに入ってくれる職人さんには、いろんな面で報いてあげたいんですよね。

――職人視点では、それはうれしいですよ。額面だけじゃなくて、別の面でカバーしてあげているんですね。でも、個人の負担として、内装職人にはどんな経費がかかりますか?
シートを切るカッター、接着剤を塗る刷毛、計測するためのスケール……消耗品が多いですね。あとはガソリン代、駐車場代とかかな。クロス工は機械をつまなきゃいけないのでバン移動ですが、僕のように床の仕上げがメインの場合は意外に身軽で、コンパクトカーで十分。
僕個人の収入はというと、大きな現場を手掛けたときは月100~200万円になることもありますが、平均すると……源泉を抜いた手取りで70~80万円といったところですね。
体を動かし、まだまだ内装業の第一線で取り組んでいく
――法人化を考えたことはありますか?
まったくないですね。法人化すると、いろいろと身動きがとれなくなることも増えてくることが分かっているので。具体的には、床張りの前の工程がずさんだったりする現場は断ることもあるんですよ。自分の技量と経験を生かして、お客さまも、そのスペースを使っていただく方も満足していただける仕事をするには、内装職人が仕上げをする前の基盤、下地がしっかりできていてこそ。
前工程がずさんだと、床のシートがすぐにめくれてしまったりすることもあるんですよ。法人化して社員を抱えると、そういった意に沿わない現場も手がけなきゃいけなくなるかもしれない。それぐらい、僕らの仕事は仕上がりのクオリティが第一なんです。社員を増やして所帯が大きくなると、全体のクオリティコントロールも難しくなるでしょうしね。

人海戦術でこなすことが求められるクロス工のような現場もありますが、こと床張りではマンパワーだけが勝負じゃないんです。
ゼネコンの海外事業部から新興国への展開のパートナーに誘われたり、一次請けの会社から「人材育成にも注力してほしい」と請われたり。いろいろなアプローチがあります。海外で勝負をするのも面白そうだし、スキー選手時代にコーチの経験もありますから、育成にも興味はあります。ただ、今のところは体を動かして励む内装の現場が好き。まだまだいろんなことを勉強して、第一線で取り組んでいきたいと思っています。