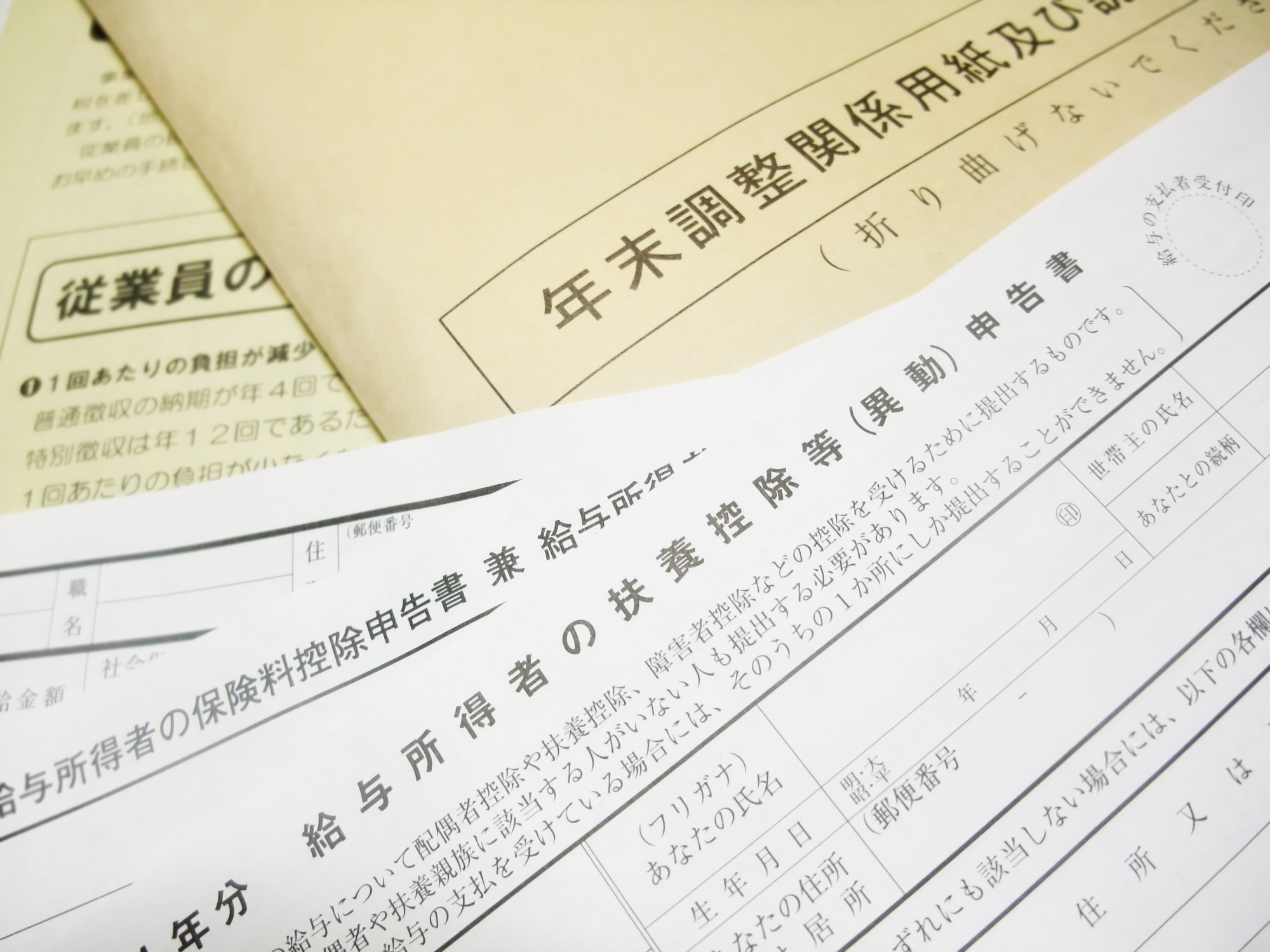毎年10月頃になると、生命保険会社や損害保険会社から確定申告や年末調整に必要となる控除証明書が手元に届きます。でも、これらの書類がどういう意味を持っているのか、きちんと理解できていない人もいるのでは? 今回は、その中でも社会保険とよばれ確定申告の際に所得から差し引かれる「社会保険料控除」について解説します。
「社会保険料控除」に該当するものは何?
「社会保険料控除」とは、社会保険料を支払った納税者が受けられる所得控除です。控除の対象となる社会保険料には、下記の種類があります。
控除の対象となる社会保険料 ・健康保険料
- 国民健康保険料(税)
- 国民年金保険料
- 厚生年金保険料
- 後期高齢者医療保険料
- 介護保険料
- 雇用保険料
- 国民年金基金の掛け金
- 厚生年金基金の掛け金
- 公務員共済の掛け金
など
社会保険料控除の控除額は?
社会保険料控除は、ほかの控除とは異なり上限がありません。つまり、1年で支払った社会保険料の全額が控除として所得から差し引かれるのです。 ただし、対象となるのは支払いが終わっているもののみ。12月31日の時点でまだ支払っていない分は、その年の社会保険料控除の対象にはなりません。逆に、過去の分をまとめて支払った場合や前納制度を活用した場合には、その全額も支払った年の社会保険料控除の対象になります。
2014年4月からは国民年金の2年前納制度が始まりました。保険料が割引になるメリットがありますし、支払った保険料の全額が社会保険料控除の対象として計算することができるため節税効果もあります。
<例>
2016年4月からの保険料で計算してみましょう。
現在、1カ月の国民年金保険料は1万6,260円、12カ月で19万5,120円です。
※実際には前納の割引制度がありますので、計算を簡単にするために19万円とします。
課税所得が19万円減るので税率を5%として計算すると、19万円×5%で9,500円の節税になります。2年前納だと38万円の保険料で1万9,000円の節税効果があります。
また、納税者が生計を一にする配偶者、またはそのほかの親族の分の社会保険料を支払った場合は、それらも控除の対象となります。家族の社会保険料を負担しているのに社会保険料控除を受けていないケースは多く見受けられます。忘れずに申告しましょう。
確定申告には社会保険料控除証明書の用意を
社会保険料控除の対象となる社会保険料の中には、確定申告時に控除証明書の提出が義務付けられているものがあります。
確定申告時に控除証明書の提出が必要な社会保険料
- 国民年金保険料
- 国民年金基金掛金
- 厚生年金保険料
確定申告時に控除証明書の提出が義務付けられていない社会保険料
- 国民健康保険料
- 介護保険料
国民年金保険料などを支払った場合は、11月中旬までには控除証明書が郵送されてきます。また、控除証明書が発行されない国民健康保険料や介護保険料を支払った場合は、納付の日付や金額の分かる振込票、納付書控えをしっかり保管しておきましょう。
国民年金保険料を2年前納した場合、全額ではなく各年に控除を分けることも可能です。
そうしたい場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除額内訳明細書」に各年分の控除額等を記入し、確定申告により控除を受ける場合は税務署に控除証明書とともに提出してください。 社会保険料控除は額が大きいうえに上限もないため、漏らさず活用したいもの。確定申告時に慌てなくて済むよう、あらかじめどんな支払いがあるかを確認しておきましょう。