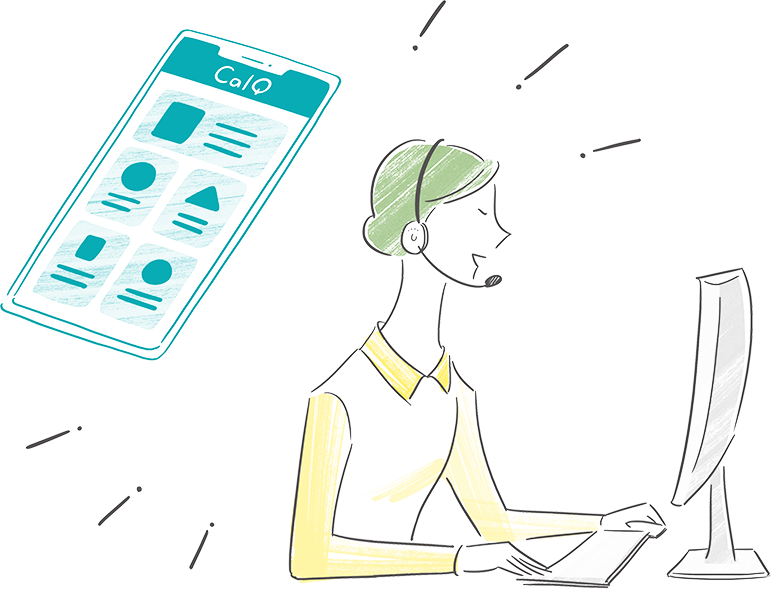本記事は退職、休職、職種変更による解約後の確定申告の手続きについて解説します。
確定申告手続きの選択について
所得税の還付の可能性があり還付を希望する場合や、退職後の勤務先での収入と合わせて手続きする必要がある場合などは、F&Mパートナーズ税理士法人に依頼する(確定申告代行料1万1,000円)か、自身で確定申告をするかを選択することが可能です。
いずれの場合も翌年2月16日から3月15日(土日祝日を挟む場合には翌日まで)に確定申告書の提出が必要です(還付申告の場合1月1日から申告が可能です)。
確定申告書を提出するステップの比較
F&Mパートナーズ税理士法人に依頼する場合と、本人が確定申告をする場合では、流れが以下のように違います。
|
1)退職月までの必要経費の領収書やレシートを必要経費保存封筒に入れて、ポストに投函 |
1)退職月までの必要経費の領収書やレシートを合計する |
| 2)生命保険会社から受け取る「支払調書」の画像を、専用アプリから送信 | 2)生命保険会社から「支払調書」を受け取る |
| 3)確定申告書の提出に承諾する | 3)確定申告書B、収支内訳書を入手する(国税庁のウェブサイトからダウンロードして印刷も可能) |
| 4)計算した結果を確定申告書に記載 | |
| 5)完成した確定申告書を税務署に提出 | |
| F&Mパートナーズ税理士法人に依頼する場合 | 本人が確定申告をする場合 |
F&Mパートナーズ税理士法人に依頼する場合の流れ
1)退職月までの必要経費の領収書やレシートを必要経費保存封筒に入れて、ポストに投函
2)生命保険会社から受け取る「支払調書」の画像を、専用アプリから送信
(※退職後他の会社に就職した場合は、その会社の「源泉徴収票」や「支払調書」も同様に送信してください)
3)確定申告書の提出に承諾する
承諾後、F&Mパートナーズ税理士法人が確定申告書を所轄の税務署に提出します。
自分自身で確定申告をする場合の流れ
1)退職月までの必要経費の領収書やレシートを合計する
自身で集めた領収書やレシートの金額を計算します。以下の点に注意してください。
- 経費項目ごとに合計金額を計算する
- 帳簿の作成
2)生命保険会社から「支払調書」を受け取る
退職後、勤務していた生命保険会社から支払調書(年間の収入金額等が記載されている書類)を受け取ります。会社から手渡しで受け取るか、自宅に郵送されます。受け取ることができる時期は退職日以降です。
3)確定申告書、収支内訳書を準備する
確定申告をするための用紙を準備します。
ただし、国税庁の「確定申告書作成コーナー」を利用する場合は、用紙は不要です。収入金額や必要経費の金額などの数字を直接打ち込むことができるためです。
「確定申告書作成コーナー」を活用しない場合、確定申告書や収支内訳書は1月中に税務署から郵送される可能性もありますが、郵送されなかった場合の入手方法は以下のとおりです。
- 国税庁のウェブサイトからダウンロードする
- 最寄りの税務署に取りに行く
4)計算した結果をもとに収支内訳書(青色申告決算書)を作成
計算結果は、以下のいずれかの方法で入力または記入します。
確定申告書作成コーナーで収支内訳書を作成する場合
必要経費の項目別に、合計金額を入力します。
収支内訳書に手書きする場合
必要経費の領収書やレシートの合計金額を項目別に、収支内訳書(青色申告決算書)に記入します。その上で、確定申告書に数字を転記します。
5)完成した確定申告書を税務署に提出
下記のうち、いずれかの方法で確定申告書を提出してください。
- 直接持参する
- 郵送する
- 電子申告をする
注意点
解約の理由によって、以下の注意点があります。
退職後仕事をしなかった場合
生命保険会社の所得のみ確定申告します。
退職後他に収入が発生した場合
条件によっては、生命保険会社の所得と退職後に発生した所得を一緒に確定申告をする必要があります。
休職している場合
生命保険会社の所得のみ確定申告します。
職種変更の場合(トレーナー等)
営業職員の事業所得と、トレーナーの固定給(給与所得)の2種類の所得を合わせて確定申告します。
必要経費の計算対象期間について
在職月までの書類を計算します。
同様に、自動車などの減価償却費も在職月をもとに計算します。
料金について
在籍月までの料金を請求します。
トレーナー等、給与所得に変更する場合は別途案内します。担当者もしくはカスタマーセンター(平日9時-17時)まで連絡してください。
サービスキットについて
解約後も税理士法人での確定申告の手続きが完了するまでは使用可能です。
サービスキットは配送先を自宅に変更します。現在登録のご住所が正しいご住所か確認してください。